なぜカテゴリー設計がGoogleアドセンスの収益に影響するのか?
この課題をテストして効果を確認してみたかった。
そこで、当記事では、それまで作成したカテゴリーをAI検索に対応した構造に作り直して、その結果を見ることにした。
多くの初心者が犯す最大の過ちは、「とりあえず思いついたカテゴリーを作ってしまう」ことです。
ぼくのブログも長年の間にこのようになり、複雑になっていた。
しかし、適当に作ったカテゴリー構造は、ユーザーの離脱率を高め、検索エンジンからの評価を下げ、最終的に収益機会を大幅に減少させることが、すでに知られています。
当記事では、AI検索になり、その時代にアドセンス収益をアップさせるカテゴリーを再構築した結果、収益がアップした効果を解説します。
初心者が陥りがちなカテゴリー設計の失敗パターン

正しいカテゴリー設計は以下の効果をもたらします。
- ユーザーの回遊率向上(平均セッション時間の増加)
- 検索エンジンでの上位表示率向上
- コンバージョン率の改善
- 長期的な収益安定化
では、失敗したカテゴリーとはどんなものなのでしょうか?
感覚的なカテゴリー作成の罠
この失敗は、ぼくが苦い体験をしています。
それをまとめると次のようなことです。
よくある失敗例:
- 日記
- 思ったこと
- おすすめ
- その他
- 雑記
この構造の問題点は、ユーザーが求めている情報にたどり着けないことです。
ユーザーは具体的な解決策や情報を求めてサイトを訪れますが、これらのカテゴリー名からは何が得られるかが全く分かりません。
過度に細分化された構造
細分化が行き過ぎると、それはマイナスに働くことが知られています。理由は、検索エンジンに負担をかけることです。その上、
各カテゴリーに属する記事数が少なく評価を下げる原因になります。
失敗例:
- WordPress初期設定
- WordPress基本操作
- WordPressプラグイン導入
- WordPressテーマ選択
- WordPressSEO設定
一見整理されているようですが、各カテゴリーに十分なコンテンツがなく、サイト全体が薄っぺらい印象を与えてしまいます。
収益化を意識したカテゴリー設計の基本原則

ユーザーの検索意図に基づく分類
今まで、カテゴリーは次の4つの検索意図を意識して設計するのが定番でした。
AI検索では、AIにカテゴリー評価も記事同様に必要ではないかと、考えました。
つめい、強いカテゴリーが必要になることです。事実、ぼくがAI検索に対応したカテゴリー編成では、カテゴリー自体が評価された結果、検索ランキング上位に表示されています。
まずは、カテゴリーの基本形を確認しましょう。
1. 情報収集型(Know)
- 「○○とは」「○○の方法」などの学習目的
- 例:「ブログ運営の基礎知識」
2. 行動実行型(Do)
- 「○○の設定方法」「○○の使い方」など実践目的
- 例:「WordPress設定ガイド」
3. 場所特定型(Go)
- 特定のサービスや場所への誘導
- 例:「おすすめツール・サービス」
4. 購入検討型(Buy)
- 商品やサービスの比較・購入検討
- 例:「商品レビュー・比較」
アドセンス収益ポイントとの連携
アドセンスでカテゴリーを収益化するために行った手法と紐づけは次の通りです。
アドセンス収益型カテゴリー
- 「基礎知識・用語解説」
- 「最新情報・ニュース」
- 「トレンド分析」
その他参考に、アフィリエイト向け、自社商品販売向けのカテゴリーを紹介します。
アフィリエイト収益型カテゴリー
- 「商品レビュー」
- 「サービス比較」
- 「おすすめツール」
自社商品販売型カテゴリー
- 「実践ガイド」
- 「成功事例」
- 「よくある質問」
具体的なカテゴリー構造の設計手順
カテゴリ構造の設計では、AIを使うとあっという間に分析して提案してくれます。
以下の項目を生成AIに投げかけてみましょう。この場合、様々な生成AIがありますが、初心者にとって使いやすく、SEO対策、AEO対策まで含め提案してくれるのが、ChatGPTです。
ターゲットユーザーの明確化
まず、あなたのサイトのメインターゲットを定義します。
例:副業ブログ運営サイトの場合
- メインターゲット:ブログで副収入を得たい会社員(30-40代)
- 抱える課題:時間がない、技術知識がない、何から始めればいいか分からない
カスタマージャーニーマップの作成
ユーザーが目標達成までにたどる道筋を整理します:
認知段階 → 興味関心段階 → 検討段階 → 購入・実行段階 → 継続・発展段階
各段階で必要な情報を整理し、それに対応するカテゴリーを設計します。
実践的カテゴリー設計例
副業ブログ運営サイトの場合
1. ブログ開設ガイド(Do型)
├ サーバー・ドメイン選び
├ WordPress設定
└ 基本設定完了まで
2. 収益化戦略(Buy型)
├ アフィリエイトASP比較
├ Googleアドセンス攻略
└ 収益最大化テクニック
3. コンテンツ制作術(Know + Do型)
├ SEOライティング
├ 記事企画の作り方
└ 効率的な執筆方法
4. アクセスアップ手法(Do型)
├ SEO対策実践
├ SNS活用術
└ 被リンク獲得方法
5. 運営ツール・おすすめサービス(Go + Buy型)
├ 必須ツール比較
├ 便利サービス紹介
└ コスト削減方法
カテゴリー設計後の最適化手順
データ分析による改善
設計したカテゴリーは以下の指標で継続的に評価します:
重要指標:
- カテゴリー別ページビュー数
- カテゴリー別滞在時間
- カテゴリー別直帰率
- カテゴリー別コンバージョン率
改善の判断基準:
- 直帰率70%以上:カテゴリー名や内容の見直し
- 滞在時間30秒以下:コンテンツの質向上が必要
- PV数が極端に少ない:統合を検討
A/Bテストによる最適化
カテゴリー名やナビゲーション構造のA/Bテストを実施:
テスト項目例:
- カテゴリー名の表現(「基礎知識」vs「初心者ガイド」)
- カテゴリー順序の変更
- サブカテゴリーの表示有無
避けるべきカテゴリー設計の落とし穴
完璧主義の罠
初心者は完璧なカテゴリー構造を最初から作ろうとしがちですが、これは失敗の元です。まずは基本的な構造で始め、コンテンツの蓄積と共に段階的に改善していくことが重要です。
競合サイトの単純な模倣
競合分析は重要ですが、単純にコピーするだけでは差別化できません。自サイトの独自性と強みを活かしたカテゴリー設計を心がけましょう。
技術的制約の軽視
カテゴリー変更は内部リンク構造やURL構造に影響します。後からの大幅な変更はSEOに悪影響を与える可能性があるため、初期段階での慎重な設計が重要です。
カテゴリー設計のチェックリスト
最終確認として、以下のポイントをチェックしましょう:
基本要件チェック
- [ ] ユーザーの検索意図に対応しているか
- [ ] 各カテゴリーの目的が明確か
- [ ] 収益化手法との連携が取れているか
- [ ] ナビゲーションが直感的か
運用面チェック
- [ ] 継続的にコンテンツを追加できる構造か
- [ ] 分析・改善しやすい設計か
- [ ] 将来的な拡張を考慮しているか
SEO面チェック
- [ ] 内部リンクが最適化されているか
- [ ] URL構造がシンプルか
- [ ] カテゴリーページ自体がSEO対策されているか
AI検索時代に求められるカテゴリーのスタイル
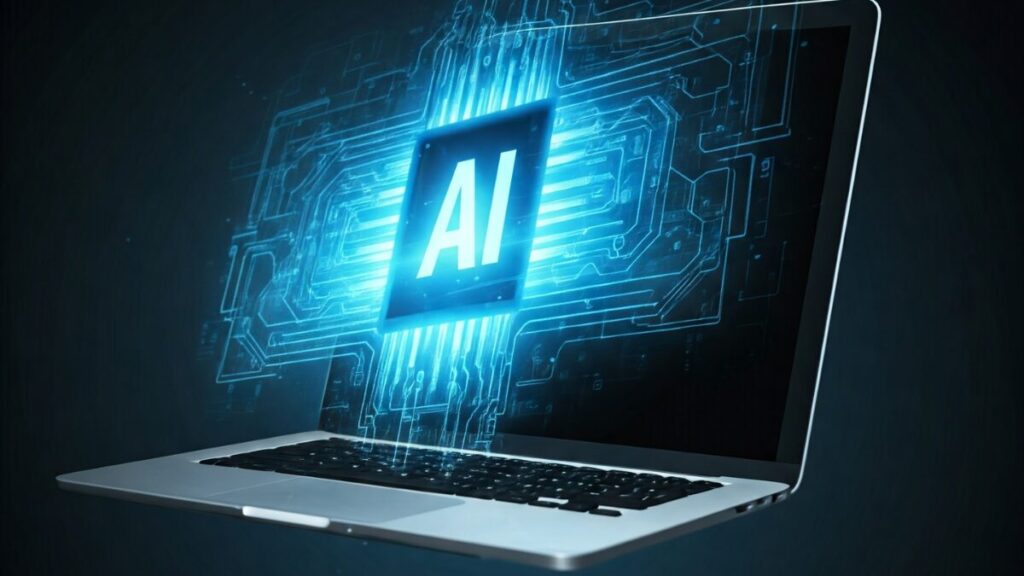
検索行動の変化に対応する
AI検索エンジンやChatGPTなどの普及により、ユーザーの検索行動が大きく変化しています。従来のキーワード検索から、より自然言語での質問形式に移行しているため、カテゴリー設計もこの変化に対応する必要があります。
従来の検索: 「WordPress 設定 方法」
AI検索時代の検索: 「WordPressを初めて使う場合、最初に何を設定すればいいですか?」
会話型検索に最適化したカテゴリー構造
AIモード時代に有効なカテゴリー設計のポイント:
質問ベースのカテゴリー名
- 従来:「SEO対策」
- AI検索対応:「検索上位に表示させるには?」
課題解決型の構造
- 従来:「アフィリエイト基礎」
- AI検索対応:「月5万円稼ぐためのアフィリエイト戦略」
ストーリー性のある分類
- 従来:「ツール紹介」
- AI検索対応:「作業効率を3倍にするツール活用法」
AIが理解しやすいカテゴリー設計
AI検索エンジンに正しく理解されるための要素
意図の明確化 各カテゴリーページに「このカテゴリーの目的」を明記し、AIが内容を正確に把握できるようにします。
関連性の強化 カテゴリー間の関連性を明確にし、AI検索結果で包括的な回答を提供できるよう設計します。
実用性の重視 AIは実用的で具体的な情報を重視するため、抽象的なカテゴリー名より、具体的なベネフィットを示すカテゴリー名を採用します。
ボイス検索への対応
音声検索の増加に備えたカテゴリー最適化:
自然な話し言葉での分類
- 「○○について知りたい」
- 「○○で困った時の解決法」
- 「○○を始める前に確認すること」
長いフレーズに対応 ボイス検索は長い質問文になりがちなため、詳細で具体的なカテゴリー名やサブカテゴリーを用意します。
AI検索時代のカテゴリーの考察
定期的なAI検索結果の確認
自サイトのカテゴリーがAI検索でどのように表示されるかを定期的にチェックし、必要に応じて調整します。
パーソナライゼーションへの対応
AIは個別のユーザーニーズに合わせた結果を提供するため、多様な検索意図に対応できる柔軟なカテゴリー構造を維持します。
継続的な学習と適応
AI技術の進歩は速いため、新しいトレンドや検索パターンの変化に敏感に反応し、カテゴリー構造を進化させ続けることが重要です。
AI検索時代においても、基本的なユーザーファーストの考え方は変わりません。しかし、ユーザーがAIを介して情報にアクセスすることを前提とした、より直感的で会話的なカテゴリー設計が求められています。
この変化に対応することで、新時代においても継続的な収益向上を実現できるでしょう。
カテゴリを再構築し、アドセンス収益アップした手法
記事が数百本に増えて、カテゴリが複雑になっていたり、現状にマッチしなくなってきました。
そこで、ブログのURLをChatGPTに教えて、現在のカテゴリを提案してもらいました。
その結果、新たなカテゴリや親子カテゴリにした方がいいか、あるいはタグで分類した方がいいか、様々なアドバイスをくれました。
編集しなおしたカテゴリはGoogleアドセンスの収益効果をアップしてくれました。昨年対比で現在2倍の収益まで増えました。
詳細は、次の中級ブロガー向け記事をご覧ください。
まとめ:継続的改善で収益最大化を実現
効果的なカテゴリー設計は一度作って終わりではありません。ユーザーの行動データを分析し、市場の変化に合わせて継続的に改善していくことで、長期的な収益向上を実現できます。
重要なのは「完璧を求めすぎず、まず始めること」そして「データに基づいて改善し続けること」です。今回紹介した手順に従って、あなたのサイトに最適なカテゴリー構造を構築し、収益化を成功させましょう。
【関連記事】




