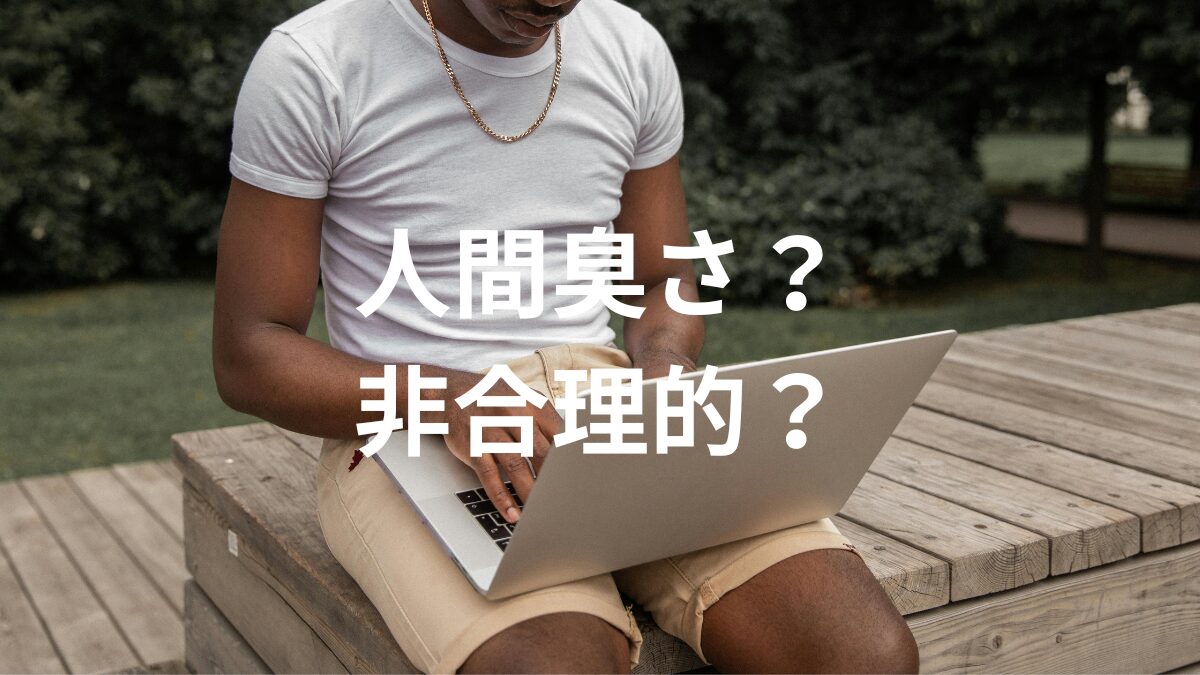すでに終わったのは「情報探索型検索」のモデルかもしれません。
かつては、ユーザーがキーワードを検索窓に打ち込み、あなたの記事がヒットし、閲覧されるというのが黄金パターンでした。記事の特徴は「~したい」「~が知りたい」「~が欲しい」といった、純粋な知識や情報の提供にありました。
これまでは、ブロガーがキーワードを調べ、夜も惜しみ汗をかいて記事を書き、ユーザーファーストの検索意図(インテント)にマッチしたコンテンツを提供してきました。これはGoogleが提唱してきた哲学であり、その本質自体は今も変わっていません。
しかし、決定的に変わったのは「ユーザーの行動」です。
生成AIの出現により、一般ユーザーが欲しがる一般的な知識や情報の提供役は、ブロガーからAIへと代わりました。AIは人間よりも速く、深く、網羅的な知識を一瞬で提供します。単純に「学んだり調べたりする知識や情報の量」において、人間がAIに勝つことは、もはや不可能な時代となりました。
知識を知りたい一般のユーザーは、検索画面の最初にAIが提供した答えに満足して帰ってしまいます。
では、ブロガーは終わったのでしょうか? いいえ、断じてそうとは言い切れません。
実は2025年現在、絶対にAIには不可能な領域が明確になり、AIの優等生的な回答に飽き飽きしたユーザーが、新たな価値を求め始めている姿が見えてきました。
今回は、これからのAI時代にブロガーに何が求められているのか、そしてAI自身がどのような記事を「価値ある情報源」として評価・引用したくなるのかを考察します。これからの時代の羅針盤として、ぜひ参考にしてください。
AIにできないこと:情報の「空白地帯」

まず、最新AIの弱点を率直にお伝えします。AIは基本的に「既存のデータの集合体」から確率論的に最適解を導き出します。つまり、データが存在しない、あるいはデータ化できない領域には手も足も出ません。
それこそが「一次情報」と言えます。
AIにできないことをまとめると、主に以下の3点です。
「今、ここ」の身体的感覚:一次体験
2025年時点で、一次体験と言われている「身体的感覚」を持つことはできません。
例えば、AIはラーメンの味を化学的に分析して解説できても、「スープを飲んだ瞬間に味わえるダシの味で、懐かしい昭和の街の食堂を思い出した」という感覚を持つことはできません。
つまり、体の五感で感じる「痛み」「快感」「苦悩」「味わい」「やる気」「挫折」などのリアリティは、人間にしか語れません。
独自の挑戦:非合理的な選択
AIはその構造から無駄が無く合理的な仕組みです。効率やデータに基づく一般的な回答を返してきます。
しかし、人間は合理的でなくとも「非合理的な選択」をします。AIにすれば無駄と判断される事柄でも「本人からすれば、何らかの利益がある」ことなどです。
予測不能な文脈の結合:セレンディピティ
AIは関連性の高い情報を結びつける構造になっていますが、人間は「昨日食べたカレー」と「明日のビジネス戦略」を突拍子もない論理で結びつけ、そこに新たな納得感を生むことができます。
この偶発的な文脈の結合こそが、AIには不可能なオリジナリティの源泉です。
人間にできること、無理なことの境界線

これからのブログで利益を生むには、どのような領域で生き延びるかを見極めることが、明暗を分けます。
人間には「無理」なこと:AIに任せるべき領域
以下の領域は、人間はAIにはかないません。この領域は、現時点ではAIに頼ることになります。
- 網羅的なまとめ情報の作成: 「おすすめクレジットカード20選」や「歴史年表」のような、情報の網羅性や正確性を競う分野。
- 一般的な用語解説: 「SEOとは?」のような、誰が書いても同じ答えになる定義の解説。
- スピード勝負の速報: 単純なニュースの要約や翻訳。
人間にしか「できない」こと:勝ち目のある領域
人間にしかできない五感で感じることの体験が、これからのブログが生き延びる領域ではないでしょうか。例えば以下の様な領域を言います。
- 一次情報の提供(N=1の体験): あなた個人の具体的な体験談、失敗談、成功のプロセス。
- オピニオン(主観的な意見): 「正しいかどうか」ではなく、「私はこう思う」「私はこう感じた」という強い主張。
- コミュニティへの共感: 読者の悩みに寄り添い、「わかるよ、つらいよね」と感情レベルで接続すること。
重要な視点: 今後のブロガーは「教科書」を作るのではなく、「ドキュメンタリー」や「エッセイ」を作る意識が必要です。
ユーザーがブログに求めていること:AI疲れの反動

2025年のネットユーザーは、AIによる「平均的で無難な回答」に便利さを感じつつも、ある種の退屈さを感じ始めています。
これを「AI疲れ」と呼びます。
ユーザーが今、ブログというメディアに求めているのは「人間味(Human Touch)」です。
具体的には、以下の領域などが挙げられます。
- 「正解」よりも「納得感」 教科書的な正解はAIが出せます。ユーザーが知りたいのは、その正解をどう現実生活に落とし込んだのかという、生々しい実践記録です。
- 「機能的価値」よりも「情緒的価値」 役に立つ情報(機能)だけならAIで十分です。ユーザーは、記事を読んで勇気をもらったり、笑ったり、怒ったりする「心の動き(情緒)」を求めています。
- 「誰が言っているか」の信頼性 情報が氾濫する時代だからこそ、「この人が言うなら信じてみよう」という、発信者への信頼(E-E-A-TにおけるAuthoritativenessとTrustworthiness)が重要視されます。
2026年に向けた考察:AIに「引用される」記事とは
ここからが本題です。
AI(GeminiやChatGPTなど)は、回答を生成する際に「信頼できる情報源」を探しています。AIに「良い記事だ」と評価され、回答のソースとして引用される(=トラフィックが流れてくる)記事には共通点があります。
それは、「AIが持っていないユニークなデータを提供している記事」です。
もしあなたが、AIがすでに持っている一般論をまとめただけの記事を書けば、AIは「知ってるよ」とスルーします。
しかし、AIが知らない「独自の検証データ」「個人的な考察」「最新の現場レポート」「具体的な自分で撮影した写真」が含まれていれば、AIはそれを貴重な一次情報源として認識し、ユーザーへの回答の中にあなたの記事へのリンクを提示します。
2026年に向けて目指すべきは以下のスタイルの事例です。
- 検証・実験型: 「AIが〇〇と言ったので、実際に100回試してみた結果」
- 逆張りオピニオン: 「世間では〇〇が正しいと言われるが、私の現場では逆だった」
- 超ニッチ特化: AIの学習データが少ない、極めて狭い領域の深掘り。
Googleアドセンスの収益に密接な関係の領域
これから先、ブログで収益を上げるためには、ブログの領域を見直すことが急務です。特にGoogleアドセンスでは、記事に広告が表示されなければ収益になりません。
つまり、ユーザーにクリックされる記事であり、それは、AIが最も欲しい一次情報だからです。
実際に体験談をもとに書いた記事はAIに引用された

実際にはもう結果が出ています。Windows10のサポートが終了した時に、ユーザーは切替えで不安になるものです。実際に私もどうしようか迷ったことがありました。
例えば、Windows11のパソコンをネットで購入したら、自分で初期設定できるのか?もし、不具合が発生したとき助けてくれるのか?などです。
また、新しいAIが発表されたときに、はたして無料で利用できるのか?登録したらどうなるのか?など。実はこれらの回答はAIに任せてしまいました。
私が書いた記事には、始まりから使えるようになるまでの、不安と解消の物語です。実際のドキュメンタリーです。
この記事は、マイクロソフトのBingで引用され、AIの回答で使われています。アクセスは1日に100件以上になる日もあります。
このように、体験ベースの記事、苦悩と解決のドクメンタリー記事は、AIが最も好み、評価すると言えます。
まとめ:人間への回帰こそが最強のSEO
情報探索型の検索モデルが終焉を迎えたとしても、人が「人の言葉」を求めることは消えません。
- AIは知識を提供する。➡ ブロガーは知恵と体験を提供する。
- AIは正解を出す。➡ ブロガーは問いを立て、感情を揺さぶる。
これからの時代、最も引用される可能性が高いのは、AIには絶対に書けない「あなたの人生そのものが反映された記事」です。情報の正確さで競うのは時代遅れなからやめましょう。
あなたの「経験」「失敗」「感情」をさらけ出して魅力ある人間臭い記事を書いてください。
それこそが、AI時代における最強のコンテンツであり、私たちが最も読みたいと思う「人間の証」なのではないでしょうか。
よくある質問(FAQ)
Q1.AIが情報を提供できるようになった今、ブログの一般的な知識やレビュー記事はもう全く意味がないのでしょうか?
A. 「全く意味がない」というより、価値が大きく低下しています。AIが提供する一般的な知識や商品のカタログ的なレビューはには勝てません。逆にAIには不可能な実践的な失敗談・成功談などの「情緒的価値」を肉付けし「あなた自身の結論」を導くための材料にしましょう。
Q2.「一次体験(N=1)」の重要性が上がるとのことですが、具体的な記事構成のヒントはありますか?
A. 構成のヒントは「ドキュメンタリー」形式です。具体的には、従来の「問題提起→解決策提示」だけでなく、「挑戦の動機」→「準備と初期の失敗」→「失敗から得た独自の知見」→「その体験を通じて感情がどう動いたか」というプロセスを詳述することです。特に、誰も書かないようなニッチな比較データや、数値化できない個人的な感覚を具体的に表現することが重要です。
Q3.AIに「引用される」ことが重要とのことですが、具体的にどのような記事を書けば引用されやすくなりますか?
A. AIは、学習データにはない「ユニークな一次情報」を高く評価します。引用されやすい記事とは、次の要素を含むものです。・独自に行った検証データやアンケート結果。・誰にも真似できない特定の環境下での現場レポート。・具体的な事例に基づいた、既存の一般論を覆す強いオピニオン。 AIは、その情報を「信頼できるソース(情報源)」として評価・活用します。
Q4.今からブログを始める初心者は、どのようなジャンルや書き方を選ぶべきでしょうか?
A. 初心者こそ、「ニッチな専門性」と「あなたの主観」を組み合わせて、AIがカバーしきれない深いジャンルを選ぶことも選択肢です。さらに、その分野への「思い」を取り入れてください。一般的なテーマを避けることが、AIとの競争から逃れるための最良の戦略です。
Q5.既存の過去記事(SEOを意識した情報探索型の記事)は、どのようにリライトすればAI時代に対応できますか?
A. 私も実戦して効果のある方法です。投稿した情報記事を「体験記事」にシフトすることが目標です。リライトは、一般論や定義の部分を大幅に短縮し、その記事テーマに関してあなたが過去に経験した具体的な失敗や成功のプロセスを追記する方法です。記事の冒頭と末尾に、そのテーマに対するあなたの独自の意見(オピニオン)や感情を加筆すれば、記事の主役が「情報」から「書き手自身」へと変わります。