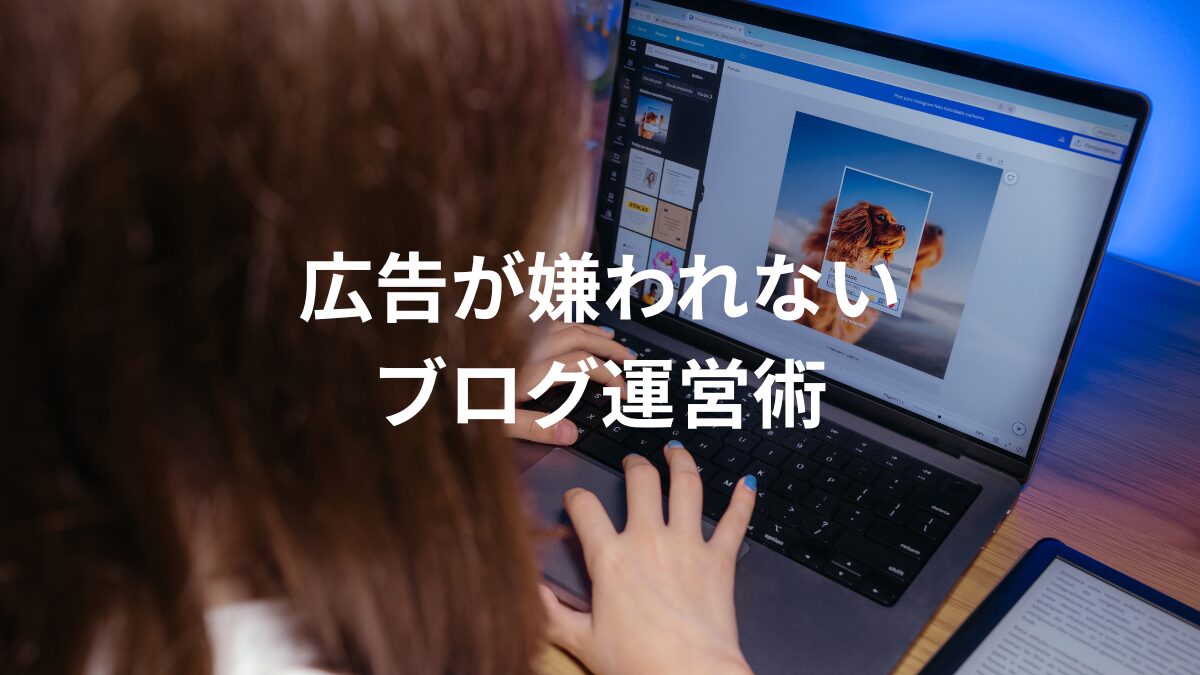ブログ収益の多くを支えるGoogleアドセンス。
しかし、近年「広告がうるさい」「読みづらい」と感じる読者が増え、広告ブロッカーを導入するケースも少なくありません。その結果、収益が下がってしまうことも…。
結論を先に言うと、広告ブロックは避けられないけれど、邪魔にならない広告構成で軽減可能です。
本記事では、広告ブロックを回避しつつ読者体験を損なわない「記事構成の工夫」を解説します。
広告ブロックが発生する主な4つの原因
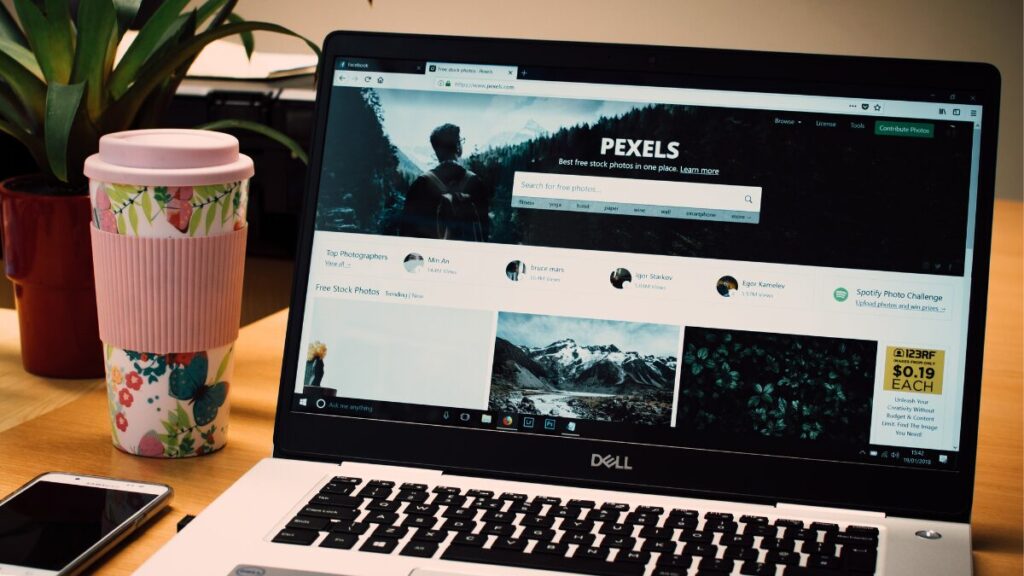
広告ブロックが発生する原因は、以下の4つが考えられます。
- 過度に目立つ広告
- 読み込み速度の低下
- 広告の比率が高いページ
- 広告嫌いの読者層
これらの原因と主な対策を順番に説明します。
1.過度に目立つ広告
ポップアップや全画面表示など目立ちすぎる広告は、ユーザーの読書体験を直接妨げます。
特にファーストビューにポップアップやインタースティシャル(全画面広告)、自動再生音声つきの動画広告などがあると、ページを開いた瞬間に不快感を覚えて離脱する原因になります。こうした体験は「広告がうるさい」と感じさせ、結果としてユーザーが広告ブロッカーを導入する動機になります。
対策(実践ポイント)
- ファーストビューを広告で埋めない:最初にユーザーが本文を認識できるようにする。
- ポップアップや全画面広告は極力避ける、どうしても使う場合はユーザーが簡単に閉じられる仕様に。
- 自動再生の音声はNG。動画広告はミュートで始めるか、ユーザー操作で再生させる。
- 「アンカー(固定)広告」や「ビルボード」などは使用するなら表示頻度・大きさを抑え、コンテンツを覆わないように調整する。
2.読み込み速度の低下
画像や広告スクリプトなどでページの表示が重いとユーザー体験が悪化し、広告ブロック導入の原因になります。特に広告ネットワークのスクリプトや大量の外部リソースは読み込みを阻害し、ページ全体のパフォーマンスを低下させます。ページ速度は離脱率やSEOにも直結するため、広告管理は速度対策とセットで考える必要があります。
対策(実践ポイント)
- 画像は圧縮・サイズ最適化(必要ならWebP化)し、遅延読み込み(lazy loading)を使う。
- 不要な第三者スクリプトを減らす。広告スクリプトは可能なら非同期(async/defer)で読み込む。
- キャッシュやCDNを導入する。サーバー側でGzip/Brotli圧縮を有効にする。
- LighthouseやPageSpeed Insightsでボトルネックを特定し、優先度の高い改善を行う。
3.広告の比率が高いページ
本文より広告が多いなどページ上に広告が多すぎると、ユーザーは「コンテンツより広告のほうが主役」だと感じ、広告ブロッカーを入れる動機になります。視覚的に広告が優勢だと信頼感も下がり、滞在時間や回遊率にも悪影響を与えます。収益を最大化するには「広告の量」ではなく「広告の質と配置」が重要です。
対策(実践ポイント)
- ページを見たときにコンテンツが主役であることを優先する(本文が明確に目立つレイアウト)。
- 画面内に表示される広告ユニット数を適切に抑える(同一画面に複数の大広告が並ばないようにする)。
- 広告の配置はコンテンツフローに沿わせ、視覚的に邪魔にならない位置にする。
- 必要に応じて「広告の種類を絞る」「広告フォーマットをレスポンシブ化」して、表示される広告が読者の興味に合うようにする。
4.広告嫌いの読者層
ITリテラシーの高いユーザーなどの読者の属性によって広告耐性は大きく変わります。ITリテラシーが高い層やプライバシー意識の高いユーザーはトラッキングや侵襲的な広告を嫌い、広告ブロッカーを積極的に導入します。ターゲットにこうした層が多い場合は、広告の出し方をより慎重に設計する必要があります。
対策(実践ポイント)
- プライバシーに配慮した広告(過度なトラッキングを伴わない広告)や、コンテンツと親和性の高い広告を優先する。
- サイトの透過的な姿勢を示す(「広告についての方針」ページを用意し、何に広告収益を使うか等を説明する)。
- AdBlockを検出した場合は強制表示ではなく、丁寧な「ホワイトリストのお願い」や、広告を減らした軽量表示の案内を行う(例:寄付や会員制で広告非表示を提供)。
- 代替収益(アフィリエイト、コンテンツ販売、サブスク)を併用してアドセンス依存を下げる。
広告ブロックは避けられない現象ですが、「読者ファーストの設計」でかなり軽減できます。まずはファーストビューの広告を見直し、ページ速度を改善し、コンテンツが主役になるレイアウトにすること。
次に、読者層に合わせた広告種類と配置を戦略的に選び、必要なら広告以外の収益源を用意することで、長期的な収益安定を図りましょう。
広告ブロックを回避する記事構成の基本方針

- 読者体験を優先する
- Googleの広告配置ルールを守る
- 本文と広告のバランスを取る
広告収益を伸ばすには、読者が「ストレスなく読める記事構成」を作ることが一番の近道です。
1. 読者体験を優先する(これが最優先)
読者がストレスなく記事を読めることを最優先に考えて広告を配置します。ページを開いた瞬間にポップアップや自動音声、画面を覆う広告が表示されると、読者は即座に不快感を覚え、広告ブロッカー導入や離脱につながります。結果的に短期的な広告表示を追うよりも、長期的な滞在時間と再訪を重視する設計の方が収益性は高まります。
実践ポイント
- ファーストビュー(ページ最初の見える範囲)は本文がまず目に入るようにし、広告は多くても1つ程度に抑える。
- ポップアップや自動再生音声は避ける。どうしても使う場合はユーザーが即閉じられる仕様にする。
- 広告はコンテンツの流れに合わせて自然に挿入する(見出し直下や段落の合間など)。
- モバイル表示での見え方を必ず確認し、スマホで邪魔にならないことを最優先に。
2. Googleの広告配置ルールを守る(推奨・ポリシー)
AdSenseは「ユーザー体験を損なわない広告配置」を前提に運用されています。ポリシー違反や規約ギリギリの配置をするとアカウントリスクに繋がるだけでなく、ユーザーの信頼も失います。推奨されている配置や表示方法を守ることで、長期的に安定した配信と収益が期待できます。
実践ポイント
- AdSenseのガイドラインに反する「誤タップを誘う配置」「ナビゲーションに似せた広告」などは避ける。
- 自動広告(Auto ads)をまず試し、問題があれば手動で微調整する。
- 広告ユニットがコンテンツに紛れ込みすぎないよう、視覚的な区切り(余白や枠)を設ける。
- 規約改定やベストプラクティスの変更は定期的に確認する(運用担当者向けの情報チェックを習慣化)。
3. 記事本文と広告のバランスを取る(コンテンツが主役)
広告の量ではなく「広告の質と配置」が重要です。コンテンツが価値を提供して初めて広告がクリックされます。本文の情報密度や読みやすさを保ちながら、読者にとって自然に受け入れられる位置にだけ広告を置くことが大切です。
実践ポイント
- 記事レイアウト例(目安):タイトル → リード(導入) → 見出し(H2)+本文(300〜600字ごとに広告を1つ検討) → まとめ → 推奨アクション(購読・他記事リンク)
- 1ページあたりの広告ユニットは「PC:3〜4、モバイル:1〜2」を目安にしつつ、ユーザー行動で調整する(サイトによって最適値は変わる)。
- 広告が本文を遮らないよう、ビジュアルの優先順位(コンテンツ>広告)を保つ。
- コンテンツ価値(独自性・実例・深掘り)を高め、広告以外のクリックや回遊を促す導線を用意する(関連記事・CTA・メルマガ登録など)。
テストと改善のループ(必須)
最適な配置はサイトごとに異なります。仮説→実施→数値確認→改善、を繰り返すことが重要です。A/Bテスト、解析ツール、ユーザーヒートマップなどで実際の行動を観察し、広告とコンテンツの最適なバランスを数値で確認しましょう。
チェックすべき指標
- ページ滞在時間、直帰率、回遊率
- 広告クリック率(CTR)とRPM(収益指標)
- ページ読み込み速度(LCP, CLS など Core Web Vitals)
- アドブロック推定率(トラフィックの中で影響を受けている割合が分かる簡易推定)
代替案(広告ブロック対策の補完)
広告ブロックを完全に無くすことはできません。そこで、広告以外の収益やオプションを用意すると収益の下振れを抑えられます。寄付ボタン、会員プラン(広告非表示)、アフィリエイト商品の強化などを検討しましょう。
実践例
- サイトの「広告について」ページを作り、透明性を示す(収益の使途など)。
- 広告非表示のサポート会員を用意(有料会員制や寄付)。
- アフィリエイト記事や自社商品ページを強化して収益の分散化を図る。
すぐ使えるチェックリスト(貼り付け用)
- ファーストビューに広告を多く置いていないか?
- ポップアップ・自動音声は無効にしているか?
- モバイル表示で広告が邪魔になっていないか?
- AdSenseのガイドラインに違反する配置はないか?
- ページ速度(LCP/CLS)が広告で悪化していないか?
- A/Bテストで配置ごとの収益・離脱率を比較しているか?
初心者向け:基本の回避策
- 自動広告の活用:Googleが最適な場所に配置してくれる
- 冒頭の広告を減らす:ファーストビューに過剰な広告はNG
- 段落の合間に自然に挿入:長文記事に適度に入れる
- モバイル表示をチェック:スマホで見にくい広告は即調整
初心者の方は、まず「広告を貼れば貼るほど収益が増える」と考えがちですが、実際には逆効果になることが多いです。広告が過剰に表示されると、ユーザーはページの閲覧を途中でやめたり、広告ブロッカーを導入するきっかけになります。そのため、広告の数は適正に保ち、記事本文をしっかり読んでもらえるようにすることが大切です。
また、広告配置は「クリックを狙う」よりも「自然に目に入る」ことを意識しましょう。記事の冒頭や途中に入れる場合も、読者がコンテンツを理解する流れを妨げないように注意する必要があります。
最後に、広告とコンテンツのバランスを意識してください。広告の割合が多すぎると信頼性を損なうため、あくまでも「記事の主役はコンテンツ」であることを忘れないことが基本の回避策となります。
中級者向け:さらに収益を守る4つの工夫
中級者むけに以下の4つの方法があります。
- 関連性の高い広告ユニットを選ぶ:記事テーマにマッチした広告を配置
- 見出しや段落に合わせて挿入:違和感なく広告が溶け込む構成にする
- レスポンシブ広告を利用:デバイスに応じて自動調整
- アンカー広告の活用:スクロールを邪魔せず自然に表示
この4つの方法について、順番に説明します。
1.関連性の高い広告ユニットを選択(例:記事テーマに合う広告のみ)
意図
読者の興味と無関係な広告はクリックされにくく、逆に不快感を生みます。コンテンツと関連性の高い広告を表示することでCTR(クリック率)と収益性が上がり、広告ブロック導入の抑止にもつながります。
実践手順
- AdSense 管理画面の「広告レビュー」「広告のカテゴリ」や「コンテンツターゲティング」を確認して、明らかに無関係・不快なカテゴリを除外する。
- 記事ジャンルごとに広告の許容カテゴリを決める(例:ガジェット記事→「家電」「ガジェット」、旅行記事→「旅行」「宿泊」)。
- 広告フォーマットは「記事内容に合うもの(in-article/ネイティブ)」を優先して作る。
- カスタムチャネルや広告ユニット名でテストグループを作り、どのユニットが高パフォーマンスかを比較する。
注意点
- 広告の「関連性」を高めすぎて表示機会が大きく減ると逆効果になることもあるので、効果測定(CTR, RPM)を必ず行う。
- 広告を選ぶ際はユーザーのプライバシーに配慮し、過剰なトラッキングを避ける設定も検討する。
2.コンテンツの見出しや段落に沿った自然な挿入
意図
広告が「突然出現する」より、コンテンツ流れに沿って自然に現れる配置のほうが読者に受け入れられやすく、誤タップや離脱が減るため収益が安定します。
実践手順
- 記事構成パターンを決める(例:リード→H2→本文300〜600字→in-article広告→H2→本文…)。
- 広告は見出し(H2/H3)直後か、段落の区切りに入れるのが自然。特に長文(2,000字以上)は段落ごとに1つ広告を入れても問題になりにくい。
- HTMLでは広告コンテナを意味的に分ける(例:
<aside class="ad-in-article">)ことで、読みやすさとレイアウト管理がしやすくなる。 - 内部リンク・関連記事・CTA(メール登録など)と広告の配置を組み合わせ、広告以外の回遊導線も同時に用意する。
具体例(構成例)
- H1(タイトル)
- リード(導入100〜150字)
- H2(見出し) → 本文(約400字) → in-article広告(1つ)
- H2 → 本文 → 関連記事ブロック → 小さめ広告
- まとめ → CTA(購読・商品紹介) → フッター広告(控えめ)
注意点
- 同一ビュー内に大きな広告が複数並ばないようにする。視覚的な広告密度が高いとブロッカーの導入や離脱につながる。
- 見出し直後に広告を置く際は「本文の導入が十分か」を必ず確認する(導入文が短すぎるとユーザーは本文を読まず広告だけを見るリスクあり)。
3.レスポンシブ広告を使い、デバイスに合わせて表示調整
意図
ユーザーはPC・スマホ・タブレットなど様々な環境で閲覧します。レスポンシブ広告は画面幅に応じて最適サイズを表示してくれるため、誤表示やレイアウト崩れを減らし、UX(ユーザー体験)を保ちながら収益を最大化できます。
実践手順
- AdSenseでレスポンシブ(自動サイズ)広告ユニットを作成する。
- サイト側で広告表示領域の最大幅を制御するCSSを用意する(例は下記)。
- モバイルとPCで見え方を必ず確認し、必要ならメディアクエリで表示有無を制御する(例:モバイルは記事内広告1つ、PCは2つまで等)。
- 表示崩れや広告のはみ出しが起きたら、コンテナ幅や余白(padding/margin)を調整する。
使えるCSS例を紹介します。記事に直接貼る場合と、WordPressの「追加CSS」や「style.css」に設定する場合の2通りです。
記事内に直接広告コードを貼る場合
<!-- 記事内広告コンテナの例 -->
<div class="ad-in-article" style="max-width:728px;margin:16px auto;text-align:center;">
<!-- ここに広告コードを貼る -->
</div>
このコードの意味と使い方は次の通りです。
<div class="ad-in-article">… 広告を囲むコンテナ。CSSやスタイルをまとめて適用できます。style="max-width:728px;margin:16px auto;text-align:center;"max-width:728px→ 広告の最大幅を728pxに制限(PC用サイズ)margin:16px auto→ 上下に16pxの余白、左右は中央揃えtext-align:center→ 広告を水平中央に配置
<!-- ここに広告コードを貼る -->→ ここにAdSenseの広告ユニットコードを直接貼ります
・使い方:
- 記事本文の該当箇所(見出し直後や段落の間など)にこの
<div>を挿入する。 <div>内のコメント部分に、AdSenseや他の広告コードをそのまま貼る。- 必要に応じてCSSで幅や余白を調整して、スマホ・PC両方で崩れないようにする。
つまり、これは 記事内に直接広告を埋め込む際のHTMLテンプレート で、CSSと組み合わせてレスポンシブに表示させることができます。
CSS に追加する場合のコード
.ad-in-article { width:100%; box-sizing:border-box; }
@media(min-width:768px) {
.ad-in-article { max-width:728px; }
}
このコードの意味と使い方は以下の通りです。
.ad-in-article {
width: 100%; /* 広告コンテナを画面幅いっぱいに広げる */
box-sizing: border-box; /* パディングやボーダーを含めて幅を計算 */
}
@media(min-width:768px) {
.ad-in-article {
max-width: 728px; /* 画面幅768px以上(PCなど)では最大728pxまでに制限 */
}
}
- 使い方
- WordPressならテーマの「追加CSS」や「style.css」に貼り付けます。
- もしくはサイト全体のCSSファイルに追加してもOKです。
- 効果
- スマホなど小さい画面では幅100%で表示され、広告がはみ出さない
- PCなど大きい画面では最大728pxに制限され、デザインが崩れにくくなる
注意点
- レスポンシブでも「広告が本文を押し出す」ような配置は避ける(特にモバイル)。
- レイアウト影響を検証するため、複数の端末(実機)での確認は必須。
4.スクロールの邪魔にならないアンカー広告の活用
意図
アンカー(スティッキー)広告は画面下部などに固定表示でき、適切に使えば目立ちすぎず収益貢献します。ただし大きすぎたり閉じづらいと逆効果になるため、設計は慎重に。
実践手順
- アンカー広告は小さめで閉じボタンが明確なものを選ぶ。ユーザーがすぐ閉じられるかを確認する。
- 長文ページや滞在時間が長い記事に限定して表示する(例:記事文字数2,000字以上、または滞在30秒以上)。
- 表示頻度を制御する(同一ユーザーに対して一定時間内は再表示しない設定が可能なら使う)。
- アンカー広告はCTAやフッターUIを遮らないこと(特にモバイルの主要操作ボタンを覆わない)。
実装の考え方
- 「表示トリガー」を工夫:ユーザーがスクロールして本文を読み始めてから表示、あるいはスクロール下部に到達したときに表示するなど。
- 「表示解除」ロジック:閉じたら一定時間(例:24時間)表示しない設定を用意するとUXが向上する。
注意点
- ユーザー操作(戻る、シェア、コメントなど)を阻害しないことが最優先。
- アンカー広告は誤タップや強制的な視認性でユーザーに反感を与えやすいので、小さめ・低頻度での運用を推奨。
参考記事:Googleアドセンスの「折りたたみ可能アンカー」広告とは?特徴と使い方を解説
テストと数値での判断(実装後に必ず行うこと)
測るべき指標
- ページ滞在時間(増減)
- 直帰率(Bounce Rate)
- CTR(広告クリック率)とRPM(収益指標)
- ページ読み込み速度(LCP/CLSなど)
- 新規vsリピーターの行動変化
実践手順
- 変更前のベースライン(直近2〜4週間)を取得する。
- 1つずつ要素を変えてA/Bテストまたは段階的テストを行う(例:in-article広告の位置をH2直後→H2下500pxに変更)。
- 1〜2週間単位で効果を集計し、定量的に判断する(統計的有意差は必須ではないが、明確な傾向が出るまで急ぎすぎない)。
- もし「滞在時間↓」「直帰率↑」などネガティブ指標が出たら即座に元に戻すか別配置を試す。
すぐ使えるチェックリスト(導入〜運用)
- 記事ジャンルごとに許容する広告カテゴリを決めた
- in-article広告は見出し/段落に自然に挿入している
- レスポンシブ広告用のコンテナを作成し端末で確認済み
- アンカー広告は小さめ・閉じやすく・表示制御を入れている
- 変更前後のデータを取得し、A/Bテストまたは段階的テストで検証している
アドセンス広告以外の収益源も検討しよう
広告ブロックを完全に防ぐことはできません。そのため、アドセンス依存を減らすことも有効です。
- アフィリエイト広告との組み合わせ
- 自分の商品・サービスの紹介
- メルマガやLINEへの誘導で読者との関係を強化
AI分析を使い広告ブロックを軽減した体験

広告がブロックされる原因は、ユーザーエクスペリエンスの問題があります。
ぼくの場合は、自動広告をブログに設定しているため、それが原因でCLS 0.25超の問題が発生しました。
その結果、広告がいろんな場所に表示されるため、記事が読みにくい状態になります。
これが、せっかくいい記事内容でもユーザーは広告を敬遠する結果を招き、それが広告ブロックのアプリを設定することにつながります。
そこで、Googleアドセンスの広告表示をユーザーにじゃまにならない様に工夫して、表示エリアを限定したり、AIによる自動広告最適化のテストをしてデータを取り対策しました。
記事構成にはAI(ChatGPT)で分析しつつ、Googleアドセンスの自動広告のAIを利用して、まさにAI × Googleアドセンス の相乗効果を試しました。
その結果、CLS 0.25超は改善し、記事の滞在時間が全体で増加し収益アップへと効果を上げています。
詳しくは以下の記事をご覧ください。初心者の方でもできる対策です。
まとめ
- 広告ブロックは避けられないが、邪魔にならない広告構成で軽減可能
- 初心者は「自動広告+基本ルール」、中級者は「戦略的な配置」で差をつけられる
- 広告以外の収益源を取り入れることで、さらに安定した収益化を実現できる
よくある質問(FAQ)
Q1:広告を減らすと収益も減りますか?
A1:短期的には減る可能性がありますが、読者体験が改善されることで長期的には収益安定につながります。
Q2:自動広告と手動広告はどちらが良いですか?
A2:初心者は自動広告がおすすめです。中級者は手動で調整してバランスをとると効果的です。
Q3:記事の冒頭に広告を置いても大丈夫?
A3:ファーストビューに多すぎる広告は離脱率が上がります。1つ程度に抑えるのが無難です。
Q4:広告を減らす代わりに何を強化すれば良い?
A4:アフィリエイトや独自サービスの紹介、リピーター獲得の導線強化がおすすめです。
Q5:広告ブロックを完全に防ぐ方法はある?
A5:完全には防げません。大切なのは「読者に受け入れられる広告配置」を考えることです。