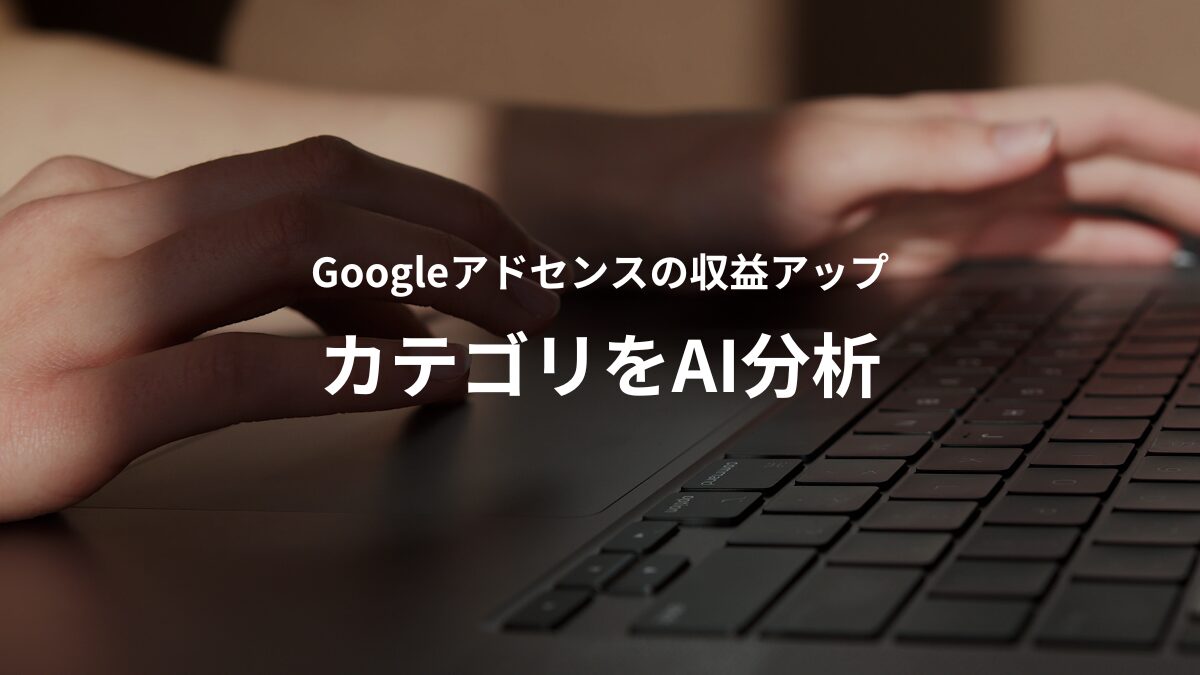ブログのカテゴリを適当に作ると、ユーザーにもGoogleにも効果的とは言えません。そこで、AIを使って現状のブログのカテゴリを分析して、効率的に閲覧できるブログ構成をする方法を紹介します。
ブログを作って運用しても、記事の評価が上がらずGoogleアドセンスの収益も増えない方におすすめの記事です。
雑然としたカテゴリの問題点
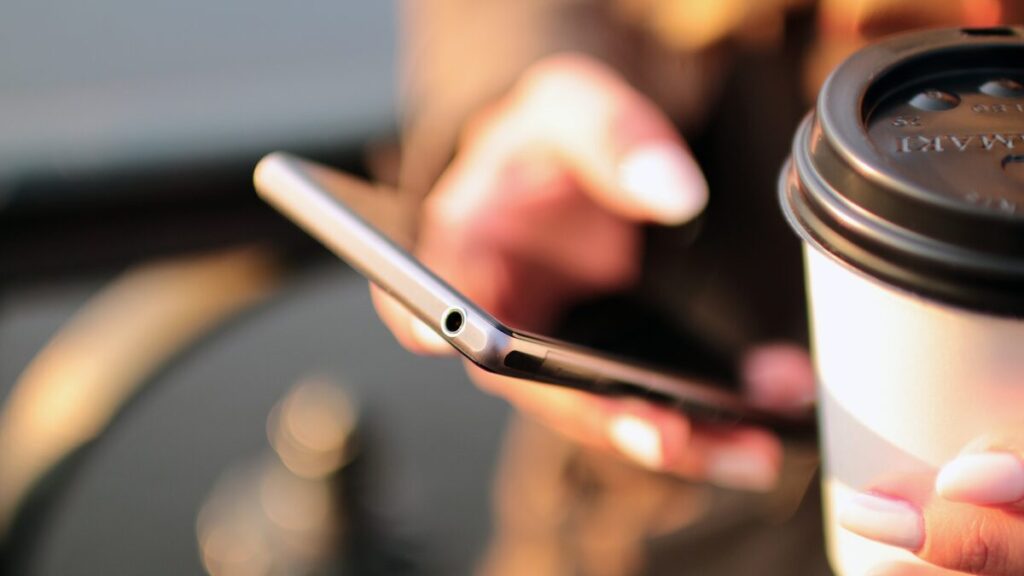
ブログを数年運営して記事数が100本を超えると、「カテゴリが雑然としている」「記事がどこに属しているのか分かりにくい」と感じる方も多いのではないでしょうか。
初心者のうちは記事数も少なく、カテゴリ設計を深く考えなくても大きな問題にはなりません。
しかし中堅ブロガーになると、記事数は数百本に増え、カテゴリの乱立や重複が目立ってきます。
よくある失敗例
- 「雑記カテゴリ」に記事が集中しすぎている
- 子カテゴリを思いつきで作った結果、1記事しか入っていない
- 収益性の高いジャンルと低いジャンルが混在している
こうした状態では、Googleから見ても「専門性が弱いブログ」と判断され、検索評価や広告配信の精度が下がってしまいます。
カテゴリが不明確なままでは、
- Googleからの評価が上がりにくい
- ユーザーが関連記事を見つけにくい
- アドセンス広告のマッチング精度も下がる
といった課題が発生し、せっかくの努力が収益に直結しません。
カテゴリを整理するメリット
そこで役立つのがAIによるカテゴリ分析です。
どのようなカテゴリ編成がユーザーにとって見やすいのか?
実は、AIを使って記事群を整理すれば、効率的に「収益が伸びるブログ構成」に作り替えることができます。
内部滞在時間が増え、ユーザーにとって多くの知識やスキルが得られます。
その結果、当然ですが、アドセンスの関連広告が表示され、有益であればあるほど広告単価の高いものが表示されます。
つまりアドセンスの収益がアップします。
AIを使ったカテゴリの分析と作り方

1. 記事群のデータを抽出
まず、現在のブログの記事タイトル・タグ・カテゴリをエクスポートします。
- WordPressなら「WP All Export」などのプラグインを使えば簡単にCSV化可能
- あるいはSearch Consoleのクエリデータも活用できます
このデータがAI分析の素材になります。
2. キーワード抽出とテキストマイニング
ChatGPTやClaudeなどのAIに「記事タイトルから共通のテーマを抽出してください」と投げると、カテゴリ候補が自動的に出てきます。
さらにPythonやGoogle Colabを使えば、形態素解析で頻出キーワードを抽出して、クラスタリング(自動分類)することも可能です。
例:
- 「掃除」「キッチン」「時短」→ 家事カテゴリ
- 「WordPress」「SEO」「テーマ変更」→ ブログ運営カテゴリ
- 「アドセンス」「収益」「クリック率」→ 収益化カテゴリ
3. 収益性のスコアリング
中堅ブロガーなら、カテゴリ再編の目的は「収益最大化」です。
そこでAIに「各カテゴリごとの収益性を評価してください」と指示し、次のデータを加味させます。
- Search Consoleでの検索ボリュームやクリック率
- アドセンスのクリック単価(ジャンル別の目安値を参照)
- 滞在時間や直帰率
これにより、「強化すべきカテゴリ」と「整理・統合すべきカテゴリ」が見えてきます。
4. カテゴリ再設計
分析をもとに、カテゴリ構造を整理します。
- 親カテゴリは5〜7個に絞る(ユーザーが理解しやすく、Googleにも専門性が伝わる)
- 子カテゴリは「深掘りテーマ」に限定
- 孤立したカテゴリは統合か削除
例:リライト前(事例はバラバラに広がったカテゴリの場合)
- 雑記
- 家事
- 掃除
- 時短アイデア
- 子育て
- 暮らし
- WordPress
- SEO
- Googleアドセンス
- 収益
リライト後(これでも、まだ特化ブログとは言えませんね)
- 家事・時短(掃除・キッチン・子育てアイデアを統合)
- 暮らし全般
- ブログ運営(WordPress・SEO)
- 収益化(Googleアドセンス・副業)
このように整理すれば、カテゴリ同士の重複が減り、記事が生き返ります。
5. 内部リンクと導線の最適化
カテゴリ整理と同時に行いたいのが内部リンクの再設計です。
- 各カテゴリトップページに代表記事をまとめる
- 関連記事の末尾に「同カテゴリの記事」リンクを設置
- AIを使って関連記事候補を抽出する
これにより、読者はカテゴリ内を回遊しやすくなり、アドセンス広告の表示回数・クリック数が自然に増えます。
カテゴリ分析の重要なポイント
AIを活用してカテゴリを整理する際には、単に分析結果を確認するだけでなく、実際のブログ運営にどう落とし込むかが重要です。
特に中堅ブロガーの場合、記事数が多いため「どこから手を付けるべきか」「どのカテゴリを優先して強化すべきか」を明確にしなければ、効果が分散してしまいます。
ここでは、収益につながるカテゴリ分析を実践するための3つのシンプルなポイントを紹介します。
1.古い記事の見直し
記事数が増えると、古い記事の情報が古くなり検索評価を下げる原因になります。AIに要約させて内容の鮮度を確認し、最新情報へリライトすることでカテゴリ全体の信頼性が向上します。定期的な棚卸しは収益性アップに直結します。
2.内部リンク整理
カテゴリ再編後は、関連記事間の内部リンクを整備することが欠かせません。記事同士を適切につなげることでユーザーの回遊率が高まり、広告の表示回数やクリック率が改善します。AIを使えば関連度の高い記事候補を自動抽出でき効率的です。
3.カテゴリ命名の工夫
カテゴリ名はSEOだけでなくユーザー理解にも直結します。難しい専門用語を避け、直感的に内容がわかる言葉を選ぶことがポイントです。AIでキーワードを分析し、検索需要の高い表現を取り入れると、検索評価と広告マッチング精度が高まります。
実践のポイント
- 半年ごとにカテゴリ健康診断
記事が増えるにつれてカテゴリは再び乱れていきます。半年に一度はAIに診断させましょう。 - カテゴリは収益軸と専門性軸の両方で評価
「収益性は低いが専門性を高められるカテゴリ」は残す価値があります。 - ユーザー目線のシンプルさを優先
難解なカテゴリ名は避け、直感的に分かる言葉を使うとリピーターも増えます。
カテゴリをAI分析して再構築した体験談

ぼくがブログのカテゴリをAI分析して再構築した体験談を紹介します。
ブログを開設して数年も経過すると、記事数は300本を超えてきました。気が付くと、途中からどんどんカテゴリは増えて来て、親子カテゴリまで複雑になりました。
数年前まではAIの存在が無かったため、自分で分析して再構築していました。
しかし、今年の生成AIの進歩は早く、利用することが一般的になってきたことから、利用してカテゴリ分析することにしました。
AIに現在のブログのタイトルとカテゴリを分析するようにプロンプトを作り投げかけてみました。利用したのはChatGPTとClaude、Geminiです。
その結果、様々なアドバイスを提案してくれ、最終的に5つにまとまりました。
その結果、記事に表示されるGoogleアドセンスの広告は質が変わり、特化したカテゴリに相応しい記事となりました。記事も質を高めてリライトした相乗効果でGoogleアドセンスのPRPMは大きく伸びました。
つまり、カテゴリはGoogleアドセンスにとって収益化では重要なことがわかりました。
まとめ
中堅ブロガーにとって、カテゴリ整理は単なる片付け作業ではなく収益最大化の戦略です。
AIを活用すれば、
- 記事群を自動で分類
- 収益性の高いジャンルを特定
- ブログ全体を分かりやすい構造に再設計
といった作業を効率的に進められます。
「記事数はあるのに収益が伸びない」と感じているなら、カテゴリをAIで見直すことが最短ルートです。
カテゴリ再編は一度手を入れると長期的に効果が出るので、ぜひ取り入れてみてください。
よくある質問(FAQ)
Q:AIでカテゴリ分析をやれば、すぐにアドセンス収益は上がりますか?
A:即効性は保証できません。AI分析で「伸ばすべきカテゴリ」が見えますが、リライト・内部リンク・導線改善などの施策を実行して数週間〜数ヶ月で効果が出ることが多いです。
Q:AI分析に使うデータは何を準備すれば良いですか?
A:記事タイトル・本文・既存カテゴリ・タグ、Search Consoleの掲載クエリやクリック数、アドセンスのカテゴリ別収益データ(可能なら)をCSVで用意すると精度が上がります。
Q:カテゴリを大幅に変えるとSEOに悪影響がありますか?
A:適切にリダイレクト(パーマリンクを変える場合)や内部リンク修正、更新日・導入文での説明を行えば長期的には有利になります。変更直後は順位変動が出ることがありますが、専門性が高まれば回復・向上します。
Q:どのくらいの頻度でAIによるカテゴリ診断を行うべきですか?
A:中堅ブロガーなら半年に1回が目安です。トピック追加や季節性の変化が大きい場合は四半期ごとのチェックも有効です。
Q:AI導入にコストや難易度はどの程度ですか?
A:簡単なキーワード抽出やChatGPTへのプロンプト実行は低コストで始められます。高精度なクラスタリングやダッシュボード化は少し技術的ですが、Google Colabや既存ツールで比較的安価に実装可能です。