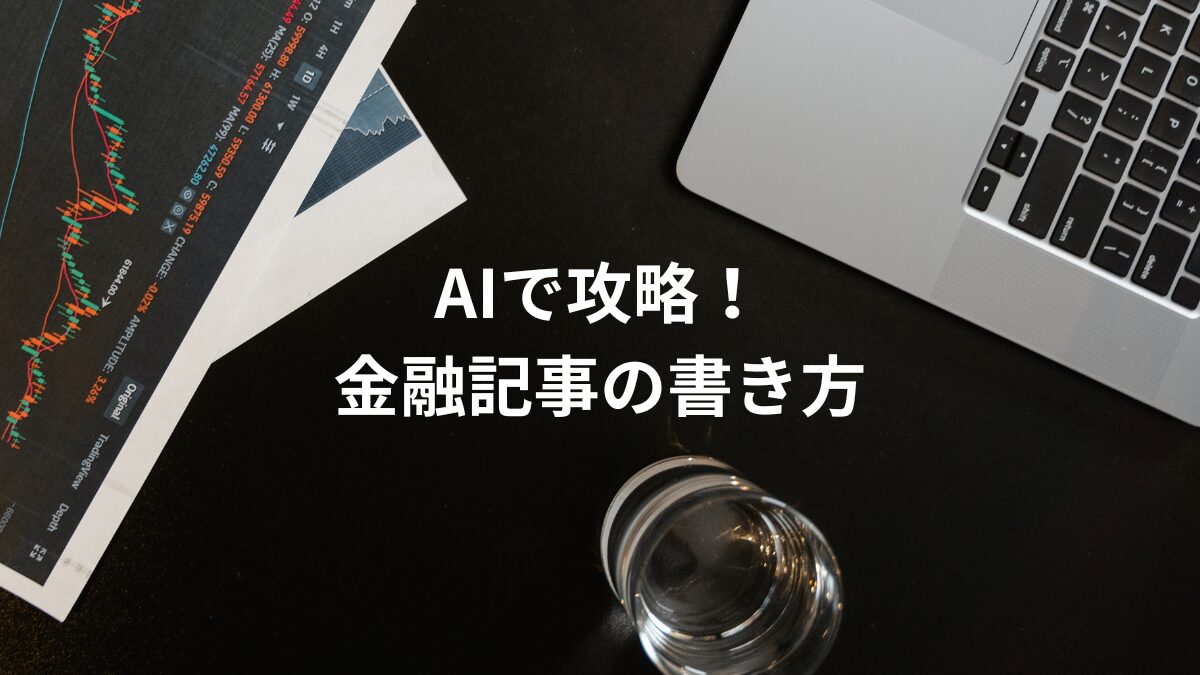結論:金融・保険ジャンルは「テンプレート化」で量産より精度を高めよう
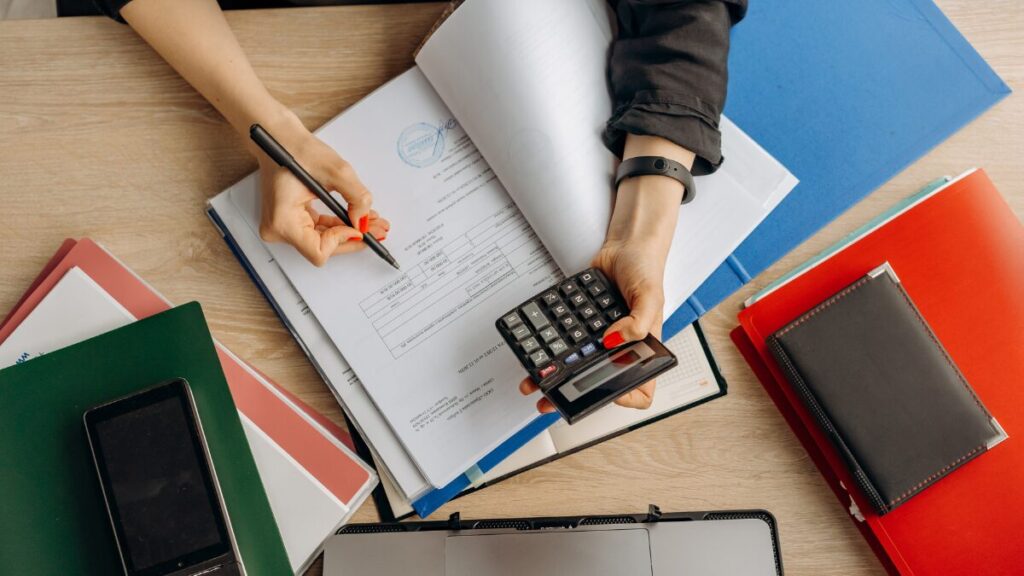
金融・保険ジャンルは、Googleアドセンスで単価(CPC)が高いことで知られています。
ただし、専門性が求められるため、やみくもに記事を増やすと「低品質」と判断されるリスクがあります。
そこで効果的なのが、ChatGPTテンプレートを使った構造化ライティング。
記事構成と入力パターンを決めておくことで、リサーチ・執筆・リライトを効率化しながら、精度の高い記事を作成できます。
金融・保険系記事が稼げる理由
金融・保険系ジャンルは、Google広告主が多く、1クリックあたりの報酬(CPC)が高めです。
たとえば以下のキーワードはアドセンス単価が高い傾向があります。
| カテゴリ | 高単価キーワード例 |
|---|---|
| 保険 | 生命保険 医療保険 自動車保険 火災保険 |
| 金融 | クレジットカード 住宅ローン 積立NISA iDeCo |
| 税金 | 確定申告 節税 副業の税金 扶養控除 |
これらは競合が多い反面、「ユーザーの悩みを的確に解決する記事」を作ることで上位表示のチャンスがあります。
ChatGPTテンプレートを使うメリット
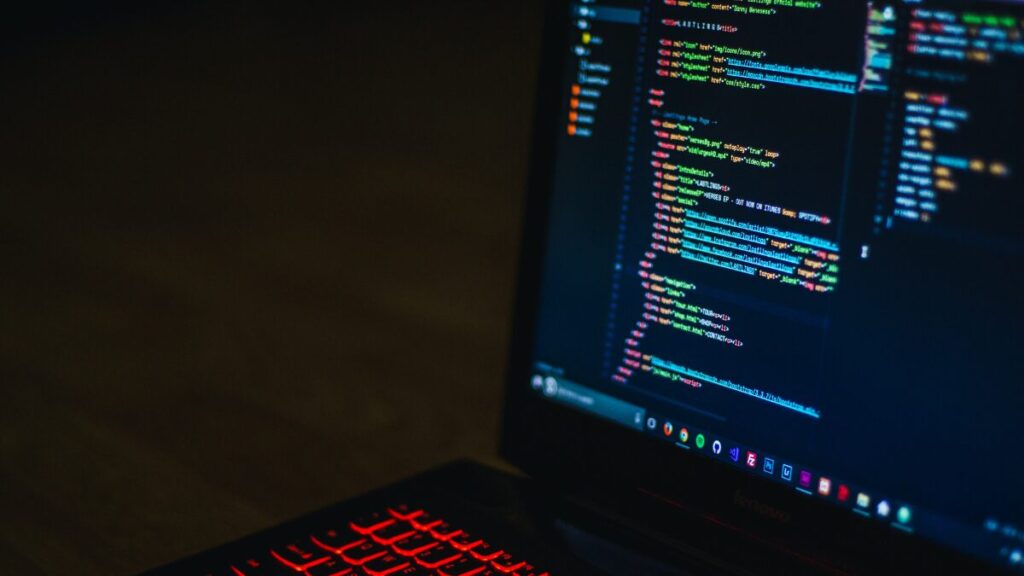
ChatGPTを活用すると、記事構成の標準化ができます。
特にテンプレート化すると、毎回ゼロから構成を考える必要がなくなり、
・見出しの一貫性
・SEOキーワードの自然な配置
・文章トーンの統一
を実現できます。
テンプレート化のポイントは次の3つです。
①「記事タイプ」を決める
- 比較記事(例:◯◯と△△どっちが得?)
- 解説記事(例:初心者向けにわかるNISAの仕組み)
- 体験記事(例:実際にiDeCoを始めてみた感想)
②「見出し構成」を固定する
H1:テーマ(例:iDeCoは本当にお得?仕組みと注意点をわかりやすく解説)
H2:結論・概要
H2:メリットとデメリット
H2:他制度との比較(NISAなど)
H2:注意点・リスク
H2:まとめと今後の動き
③「入力プロンプト」を保存する
ChatGPTに以下のような指示をテンプレート化しておくと、再利用が可能です。
「以下の構成に沿って、金融初心者にもわかりやすい文章を作成してください。
内容は事実に基づき、公式データを引用する箇所を明示してください。」
効率的なライティング手順
ステップ1:テーマを選定
「検索ボリューム」×「競合性」でテーマを決めます。
例:「iDeCo 節税」→競合が多いが、リライト余地がある
例:「確定申告 ブログ収益」→特定層に響く
ステップ2:公式データをリサーチ
ChatGPTに「参考URLを提案させる」ことで、リサーチの方向を明確にします。
たとえば、
「金融庁公式サイトからNISA制度の最新情報をまとめてください」
と指示するだけで、概要を整理できます。
ステップ3:テンプレートで本文生成
テンプレートに沿って、ChatGPTで初稿を生成。
不自然な箇所や冗長表現は削り、「自分の体験」や「感想」を1文でも入れると、E-E-A-Tが高まります。
ステップ4:AI感を消すリライト
- ChatGPTに「もっと人間らしい口調に」と依頼
- 自分の経験談や事例を追記
- 図解や表を追加する
SEO的に有効なテンプレート設計
SEO上位を狙うには、テンプレートの中に次の要素を盛り込みます。
| 要素 | 目的 |
|---|---|
| 「結論ファースト」導入 | クリック後の離脱防止 |
| 「データ+体験談」 | 信頼性アップ(E-E-A-T) |
| 「よくある質問(FAQ)」 | リッチリザルト対策 |
| 「内部リンク挿入枠」 | 回遊率・滞在時間の向上 |
たとえば、記事末尾にFAQを追加するテンプレートを用意しておくと、自動生成時にも自然に挿入できます。
テンプレート例
ChatGPTプロンプト例(コピペOK)
「次のテーマについて、SEOを意識したブログ記事構成と本文案を作成してください。
・テーマ:〇〇(例:iDeCoの始め方)
・ターゲット:制度をまだ理解していない人
・目的:初心者でも安心して始められるように解説
・構成:結論→メリット→注意点→まとめ
・トーン:専門的すぎず、信頼感のある口調で」
これを保存しておけば、どのテーマにも使い回しが可能です。
金融・保険系記事で注意すべき点
Googleは金融系を「YMYL(Your Money or Your Life)」分野として扱います。
つまり、誤情報はペナルティの対象になる可能性があります。
対策としては、
- 出典(公式サイト・金融庁・国税庁など)を必ず明示
- AI生成文は「一次情報で裏付ける」
- 個人の感想と事実を明確に区別する
これらを徹底することで、AI記事でも信頼を確保できます。
ハルシネーションの危険性を体験

AIが事実に基づかない、誤った情報を生成する現象は、一般的に「ハルシネーション(hallucination)」と呼ばれています。
ハルシネーションは、まだまだ少ないとは言えません。実際に、いままでAIで作成した記事を読み返してみると、事実と異なる記載を見つけることがあります。
生成された記事をチェックすることは、必須と言えます。
- AIで調べた過去の内容を別記事で流用してしまう
- 似ている出来事を一緒にしてしまう
- スペックなどのデータを間違うことがある
特に今回ご紹介した金融・保険系の記事をAIが書く場合、出力した内容をしっかりチェックし、ミスや勘違いをしていないかどうか確認することが必要です。
ユーザーに間違った情報を提供することが無いように注意しましょう。
よくある質問(FAQ)
Q1. ChatGPTで金融・保険系の記事を書くのは危険ではありませんか?
A. 公式データ(金融庁・国税庁・厚労省など)を必ず参照すれば問題ありません。AIの出力だけに依存せず、一次情報を裏付けとして使うことが大切です。
Q2. テンプレートはどのように保存すればいいですか?
A. よく使うプロンプトをメモアプリやGoogleドキュメントにまとめておき、テーマ別に分類しておくと便利です。ChatGPTの「カスタム指示」機能を使えば、さらに効率的です。
Q3. 金融ジャンルは初心者でも書いて大丈夫?
A. 専門家でなくても、体験談や制度の理解を中心にした記事なら問題ありません。正確な出典を明示し、誤情報を避けることがポイントです。
Q4. 金融・保険系記事で収益を上げるコツは?
A. 「比較・節約・シミュレーション」など、ユーザーの“行動”につながるテーマが効果的です。FAQを含めて記事の滞在時間を伸ばすとアドセンス評価も向上します。
Q5. ChatGPTで作った記事はアドセンス審査に通りますか?
A. オリジナリティと信頼性を重視すれば通過可能です。AI生成だけでなく、あなた自身の経験や意見を1文でも入れることが重要です。
まとめ|テンプレート化で「狙って書く」時代へ
金融・保険ジャンルは、単価が高くても「正確さ」と「信頼性」が命。
ChatGPTテンプレートを使えば、
- 記事構成を自動化
- リサーチ時間を短縮
- 品質のばらつきを防止
が実現できます。
「AIを使ってラクをする」のではなく、
「AIで正確に、効率よく伝える」という発想が収益アップへの近道です。